風邪やインフルエンザ、気管支炎などにかかった後、咳だけが長引いて眠れないようなときにおすすめの漢方薬が『竹筎温胆湯(ちくじょうんたんとう)』です。

風邪をひいてから咳がずっと続いているよな時で、特に眠ろうとして横になると咳が出だして眠れないような時にはどんな漢方薬がいいの?


そんな時には『竹筎温胆湯』がおすすめです。
今回はこの漢方薬について解説してみますね!
風邪とインフルエンザの違いとは?

一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で全身症状はあまり見られません。
風邪の場合は発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。
インフルエンザに罹患すると38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れます。
併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。
子供の場合は、まれに急性脳症を発症したり、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴うなど重症化することがあります。
(引用:厚生労働省ホームページ)
百日咳とは?

百日咳の定義
百日咳(ひゃくにちぜき)は、正式には「百日咳菌」または「ボルデテラ・パータシス菌(Bordetella pertussis)」によって引き起こされる高度に伝染性の呼吸器感染症です。
この病気は、特に子供に影響を及ぼし、持続する激しい咳の発作を特徴としています。
その名の通り、咳が長期間(通常6〜10週間、場合によっては3ヶ月以上)続くことから「百日咳」と呼ばれています。
原因となる細菌(ボルデテラ・パータシス)
百日咳の原因となるのは、「ボルデテラ・パータシス(Bordetella pertussis)」という細菌です。
この細菌は、人の呼吸器に感染し、毒素を生成して咳の発作を引き起こします。
ボルデテラ・パータシスは以下のような特徴を持っています:
- 細菌の性質:グラム陰性の小型の桿菌(棒状細菌)です。
- 毒素の生成:この細菌は、百日咳毒素(pertussis toxin)やアデニル酸シクラーゼ毒素(adenylate cyclase toxin)など、複数の毒素を生成します。これらの毒素は、気道の上皮細胞に損傷を与え、強い咳反射を引き起こします。
- 増殖環境:ヒトの呼吸器粘膜に特化して増殖し、他の動物には感染しにくい特性があります。
伝染力と感染経路
百日咳は非常に伝染力が強い病気です。
以下にその伝染力と感染経路について詳しく説明します。
伝染力
- 高い感染力:百日咳は非常に伝染性が高く、感染者との接触によって容易に広がります。感染者が咳をしたりくしゃみをしたりする際に、空気中に放出された飛沫を通じて他人に感染します。
- 感染期間:感染者は、症状が出る前の潜伏期間(7〜10日)から症状が現れた後の初期(約2週間)までの期間に最も感染力が高いとされています。
感染経路
- 飛沫感染:百日咳の主な感染経路は飛沫感染です。感染者が咳やくしゃみをする際に放出される微小な飛沫(エアロゾル)を他の人が吸い込むことで感染が広がります。
- 直接接触:感染者の唾液や鼻水などの分泌物がついた手や物に触れ、その手で口や鼻を触ることでも感染する可能性があります。
感染しやすいグループ
- 乳幼児:特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんは、百日咳に対する免疫が未発達であるため、感染しやすく重症化しやすいです。
- ワクチン未接種者:百日咳ワクチンを接種していない人、または接種から時間が経ち免疫が低下した人は、感染のリスクが高まります。
予防策
- ワクチン接種:最も効果的な予防策は、定期的なワクチン接種(DPTワクチンやTdapワクチン)です。これにより、感染を防ぎ、重症化を防ぐことができます。
- 衛生管理:手洗いやマスクの着用など、一般的な感染症対策も重要です。

「Tdapワクチン」とは、成人用三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風混合)ワクチンんことです!
Tdapワクチンとは
思春期や成人に接種しても疼痛などの副反応が出にくい成人用三種混合ワクチン(百日咳・ジフテリア・破傷風混合ワクチン)があります。
これは、一般に「Tdap(ティーダップ)」と呼ばれるワクチンです。
小児に用いる三種混合ワクチンは、破傷風トキソイドの成分が成人に必要な量より少なく、逆にジフテリアトキソイドの成分が多いため、成人に接種すると疼痛などの副反応が出やすい傾向があります。
Tdapワクチンはこれらの成分量を成人向けに調整しており、副反応が出にくい設計になっています。
米国では、妊娠中の接種も承認されており、新生児の百日咳予防を目的に妊娠後期の接種が推奨されています。
しかし、日本では未承認のため、接種を希望する場合は輸入未承認ワクチンを取り扱っている医療機関に相談する必要があります。
日本では、小児用の成分比である三種混合ワクチン(トリビック®)が成人も含めた治験を経て全年齢向けに承認されています。
百日咳の治療法の現状
現在、世界的に見ても百日咳の咳嗽を完全に止める治療法は確立されていません。
一般的に使用される西洋薬の気管支拡張薬、去痰薬、中枢性鎮咳薬(コデインリン酸塩など)は、百日咳の咳嗽には効果がありません。
カタル期の治療
カタル期にマクロライド系抗菌薬を投与することが、ほぼ唯一の効果的な治療法です。
しかし、咳が出始めてから抗菌薬を投与しても、患者本人の咳を止めることはできず、他者への感染予防には寄与しますが、症状の改善にはつながりません。
再興感染症としての百日咳
現在使用されている百日咳ワクチンの効果減弱により、百日咳は先進国でも再興感染症となっています。
特に0歳児にとっては致死的な疾患であるため、注意が必要です。
百日咳の流行状況
百日咳は珍しい疾患ではなく、コモンディジーズとして流行しています。
早期診断と治療
百日咳抗体IgM(M抗体)と百日咳抗体IgA(A抗体)を用いて百日咳を早期に診断し、迅速な治療を行います。
漢方薬による治療
漢方薬治療として、『竹筎温胆湯(ちくじょうんたんとう)』を使用し、必要に応じて『麦門冬湯(ばくもんどうとう)』を併用します。
漢方薬治療によって、発症1週間以内であれば1週間で、発症10日を超えた場合でも2週間以内に、百日咳の咳嗽を止めることが可能です。
【竹筎温胆湯】の生薬構成(ツムラ)
柴胡(サイコ)、竹筎(チクジョ)、茯苓(ブクリョウ)、麦門冬(バクモンドウ)、陳皮(チンピ)、枳実(キジツ)、黄連(オウレン)、甘草(カンゾウ)、半夏(ハンゲ)、香附子(コウブシ)、生姜(ショウキョウ)、桔梗(キキョウ)、人参(ニンジン)
【竹筎温胆湯】の効能効果(ツムラ)
インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても気分がさっぱりせず、せきや痰が多くて安眠が出来ないもの
【竹筎温胆湯】の特徴・説明
- 『竹筎温胆湯』は切れにくい痰が出て、咳き込む場合が使用の目安になります。
「麻黄」が含まれないために、同様の症状のときに使用される『麻杏甘石湯』、『五虎湯』などで胃腸障害が出やすいひとに使用するとよいです。
- 『竹筎温胆湯』は不眠を伴う場合に使用されますが、西洋薬などの睡眠剤のように単なる眠気を催すような作用は期待できません。
中医学では ”胆” が冷えると眠れないと考えられていたため、”胆” を温める作用があるということが『温胆湯』の由来のようです。
ちなみに ”胆” は現在使用されている ”胆嚢” とは異なる概念です。
- 『竹筎温胆湯』の味は表現法が難しいですが、渋いです。
【竹筎温胆湯】のクリニカルパール
クリニカルパール(Clinical pearl)とは、経験豊富な臨床医から得られる格言のようなものです。
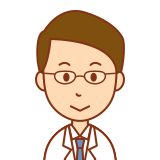
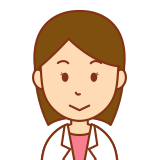
PTSDには ”EMDR治療” が効果があるとされている治療法の一つです。
また、イップスは、ブレイン・スポッティングというEMDR治療の改訂版が有効です。
(引用:漢方.jp)
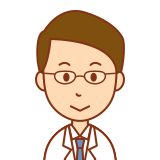
色々なことにビクビクしているような人に『竹筎温胆湯』がおすすめです!
(引用:漢方.jp)
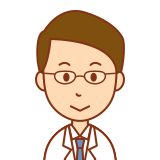
『竹筎温胆湯』は中医学では ”発熱性疾患の経過に生じる痰熱上擾(たんねつじょうじょう)” ”痰熱上擾で肝気鬱結の症状と気陰両虚の症状を伴うもの” に使用する漢方薬です。
”肝気鬱結(かんきうっけつ)” とはストレスなどによって自律神経あ乱れた状態のことを意味しています。
(引用:がんじゅうふぁみりー)
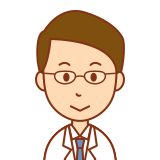
”痰熱上擾(たんねつじょうじょう)” とは病因となる粘稠な余分な水分と熱が結びついたものが上昇して頭や胸(肺)などの身体の上部をかき乱した状態を意味しています。
分かりやすく解説すると、ストレスなどによって脳や交感神経が興奮した状態になり、胃腸の働きが悪化します。
胃腸の働きが悪化することで ”痰” が生まれ、興奮によって生じた ”熱” と結びついて ”痰熱” になります。
熱は上昇する性質があるため身体上部である脳や肺をかき乱すのです。
暴飲暴食などが原因で、余分な水分と熱が余った状態になり、胸の不快感・吐き気・めまい・頭が重い・寝つきが悪い・眠りが浅い・イライラ・驚きやすい・動悸・粘り気のある痰などの症状があらわれます。
(引用:がんじゅうふぁみりー)
【竹筎温胆湯】の注意点
むくみ・体重増加・血圧上昇などが現れた場合は医師・薬剤師に相談するようにしてください。
【竹筎温胆湯】の入手方法
- 病院で処方してもらう
- ドラッグストアや楽天・Amazonなどのインターネットで購入できます。


「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。
代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。
漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。
また、わんこの健康も見逃しません。
わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。
「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?
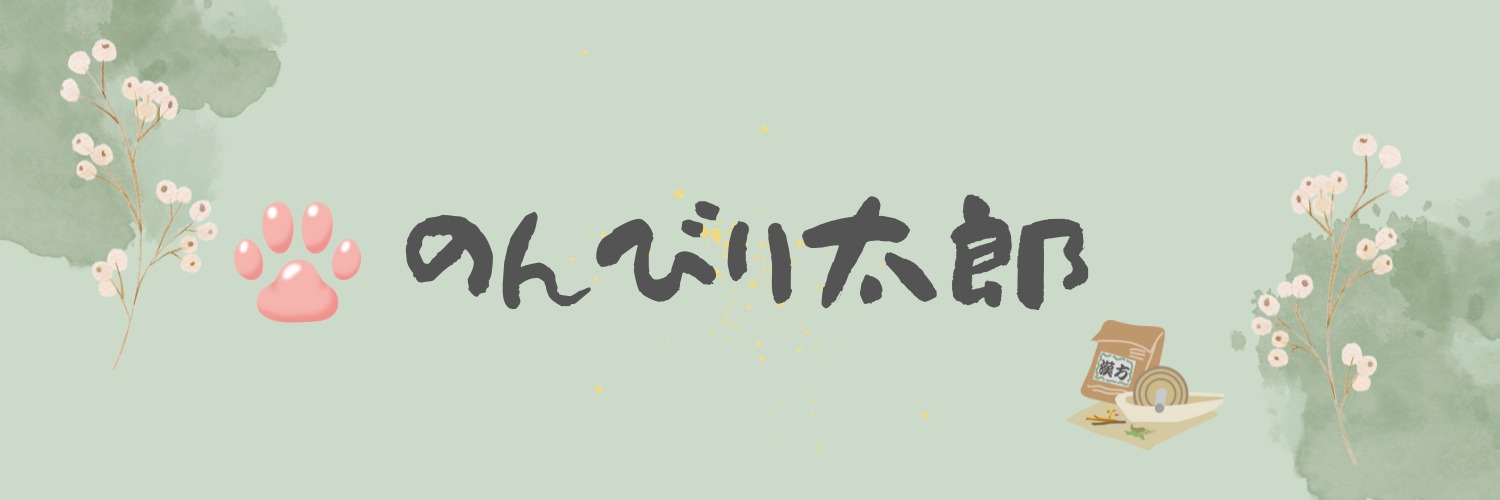



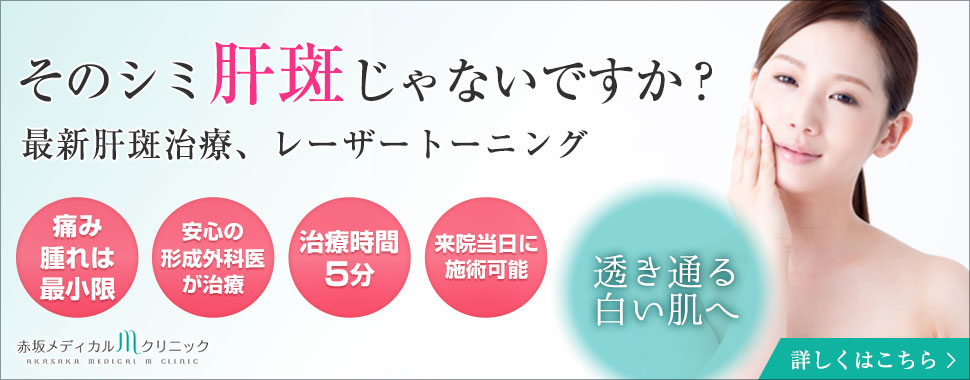

コメント