気管支炎・気管支喘息などの痰が絡むような咳が出る時におすすめの漢方薬が『五虎湯(ごことう)』です。

気管支炎・気管支ぜんそくなどに使われる漢方薬は多いので、どの漢方薬がいいのか悩むことも多いと思います。
今回は『五虎湯』をはじめとした、咳が出るようなときに使用する漢方薬を紹介していきたいと思います。

気管支喘息とはどのような状態なの?
気管支喘息(喘息)は空気の通り道(気道)に炎症(ボヤ)が続き、さまざまな刺激に気道が敏感になって発作的に気道が狭くなる(大火事)ことを繰り返す病気です。
日本では子供の8~14%(赤澤 晃ガイドラインの普及効果QOLに関する全年齢全国調査に関する研究報告書 2008年)、大人では9~10%(Fukutomi Y. Int Arch. Allergy Immunol 2010)が喘息です。高年齢で発症する方もおられます。
ボヤの原因はチリダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルギーによることが多いのですが、その原因物質が特定できないこともあります。
発作的に咳や痰が出て、ゼーゼー、ヒューヒューという音を伴って息苦しくなります。
これを喘息発作と呼びます。
夜間や早朝に出やすいのが特徴です。
(引用:日本呼吸器学会)
肺に効くツボのポイントは『肺経』!ツボ押しで咳・喘息・気管支炎のつらさを回避できる⁉

「肺経」の正式な名前は「手の太陰肺経(たいいんはいけい)」と呼ばれます。
この気の巡りが悪くなった状態は「肺虚」と呼ばれて、息苦しさや咳が出る原因ともいわれています。

「肺経」を刺激して、気の通りをよくする代表的なツボが『尺沢(しゃくたく)』『孔最(こうさい)』なんだって!

『尺沢(しゃくたく)』:せき、喘息などに有効です。

『孔最(こうさい)』:
激しい咳や喘息以外にも、痔疾の出血や痛みに有効です。
また、鬱でなかなか気力の出ないような場合にも有効です。
【五虎湯(ごことう)】の生薬構成(ツムラ)
石膏(セッコウ)、杏仁(キョウニン)、麻黄(マオウ)、桑白皮(ソウハクヒ)、甘草(カンゾウ)
【五虎湯(ごことう)】の効能効果(ツムラ)
せき、気管支ぜんそく
- 麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう):発作時に使用
- 小青竜湯(しょうせいりゅうとう):咳より鼻水などが目立つときに
- 苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにとう):小青竜湯の虚証版(裏処方)
- 神秘湯(しんぴとう):気うつ傾向の症状があるときに
- 柴朴湯(さいぼくとう):
症状が落ち着いてきた寛解期に使用。
気分がふさいでいるときに適している。発作予防にもOK。
【五虎湯(ごことう)】の特徴・説明
- 『五虎湯』は気管支喘息・気管支炎などに使用され、粘稠痰によりこれを排出するために咳き込むような時が目安となります。

「桑白皮」が含まれていると ”子供向け” になります。
小児の喘息には『麻杏甘石湯』より『五虎湯』を使用することが多いです。
- 『五虎湯』の味は表現法が難しいですが、甘くて渋いです。
【五虎湯(ごことう)】のクリニカルパール
クリニカルパール(Clinical pearl)とは、とは経験豊富な臨床医から得られる格言のようなものです。
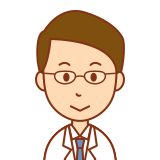
【五虎湯(ごことう)】の注意点
むくみ・体重増加・血圧上昇などが現れた場合は医師・薬剤師に相談するようにしてください。
【五虎湯(ごことう)】の入手方法
- 病院で処方してもらう
- ドラッグストアや楽天・Amazonなどのインターネットで購入できます。


「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。
代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。
漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。
また、わんこの健康も見逃しません。
わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。
「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?
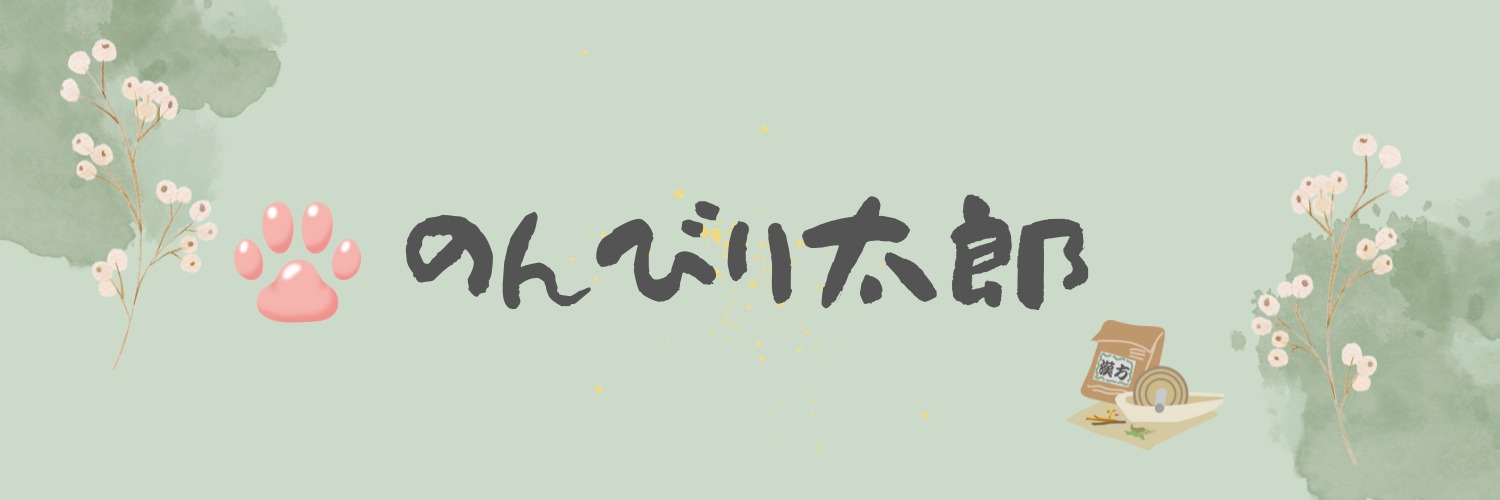



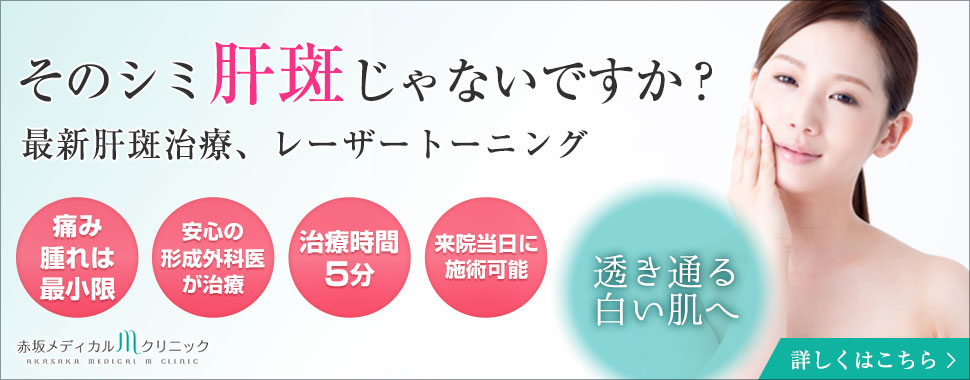

コメント