寒冷などによって、手足の先が冷えてつらい思いをしている方におすすめの漢方薬が『当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)』です。
呪文・早口言葉のようなネーミングの漢方薬ですね!

冬の寒い時期には、指や耳たぶが赤く腫れたり、痒くなってしまうことあるんだよね…。


そう言えば、子供の頃はしもやけになっていたような…。
しもやけや末梢の冷えにおすすめの漢方薬が【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】なのです。

凍瘡(しもやけ)とは?どんな時にしもやけになりやすいの?

「凍瘡」とは、いわゆる「しもやけ」のことです。
冬期間に気温が4~5度で一日の気温の差が10度以上になると、しもやけを起こしやすくなると言われています。
血行の悪くなりやすい場所、すなわち手足の指先、耳朶(耳たぶ)、頬、鼻などに症状が出やすいのです。
しもやけになると皮膚が赤く腫れあがり、ひどい時には水ぶくれを起こすこともあります。
痒みを伴うことが多く、入浴することによって痒みが強くなることも特徴のひとつです。
しもやけは子供がなりやすいのですが、女性の場合、大人になっても繰り返す人がいます。
しもやけの原因は冷たい空気にさらされることなのですが、同じように寒気にさらされてもしもやけにならない人もいます。
しもやけを起こしやすい人と起こしにくい人がいることが知られています。
冷気にさらされた後の血流の障害の程度と、そこからの回復には遺伝的な差があって、しもやけになりやすい体質の人となりにくい体質の人がいると考えられているのです。
凍瘡(しもやけ)の治療にはどのようなものがあるの?
凍瘡(しもやけ)は寒冷な環境で起こる血管障害で、手足の指先や耳、鼻、頬などが赤く腫れて痛みやかゆみを伴う状態です。
治療には以下のような方法があります。
1. 温熱療法
温熱療法は、患部を温めることで血行を改善し、症状を軽減します。
- 温水に浸す: 患部を40度程度の温水に浸す。数回繰り返すことで血行が促進されます。
- 温湿布: 温かい湿布を患部に当てることで血行を良くします。
2. 保湿と保護
保湿と保護は、皮膚の乾燥を防ぎ、バリア機能を維持するために重要です。
- 保湿クリームや軟膏: 尿素やヒアルロン酸、セラミド、ビタミンEを含む保湿クリームや軟膏を使用します。
- 保護手袋や靴下: 外出時に手袋や厚手の靴下を着用し、冷えを防ぎます。
凍瘡(しもやけ)の治療には、通常ビタミンEの塗り薬が使われます。
症状が強い場合や広範囲にわたる場合、毎年しもやけを繰り返す場合などには、ビタミンEの飲み薬も有効です。

ビタミンE配合の塗り薬で有名な商品が『ユベラ🄬軟膏』です。
ユベラ軟膏は、血流の改善と皮膚の保護という2つの効果により、しもやけやかかとのカサカサの改善が期待できます。
ユベラ軟膏🄬には、血行促進作用があるビタミンEと、 角化調節作用があるビタミンAが配合されています。

OTC医薬品でビタミンE配合の商品は『ザーネ🄬クリーム』『ザーネ🄬スキンミルク』【エーザイ】です。
有効成分の天然型ビタミンEとグリチルリチン酸ニカリウム(消炎成分)が皮フから直接吸収され、あれてカサつく手・肌をしっとりなめらかに保ってくれます。
3. 薬物療法
薬物療法は、炎症やかゆみを軽減するために使用されます。
- 抗ヒスタミン薬: かゆみを抑えるために用いられます。
- ステロイド外用薬: 炎症を軽減するために使用します。
- 血行促進薬: ビタミンEやプロスタグランジン製剤が使われることがあります。
4. 漢方療法
漢方療法も凍瘡の治療に効果的です。
以下のような漢方薬が用いられます。
- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう): 冷え性や末端の血行不良に効果的です。
- 温経湯(うんけいとう): 血行を改善し、冷えや痛みに効果があります。
5. その他の治療
その他の治療方法として、以下のようなものがあります。
- 赤外線療法: 赤外線を患部に照射し、血行を促進します。
- マッサージ: 優しくマッサージを行い、血流を改善します。
予防方法
予防方法として、日常生活での注意が重要です。
- 適切な服装: 寒い環境では暖かい服装を心がけ、特に末端を冷やさないようにする。
- 運動: 適度な運動で全身の血行を良くし、冷えを防ぐ。
- バランスの取れた食事: ビタミンEやビタミンCを多く含む食品を摂取し、血行を促進する。
小まとめ
凍瘡(しもやけ)の治療には温熱療法、保湿と保護、薬物療法、漢方療法、その他の治療方法があります。
また、日常生活での予防も重要です。
適切な治療と予防を行うことで、凍瘡の症状を軽減し、再発を防ぐことができます。
参考文献
・日本臨床皮膚科医会
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】の生薬構成(ツムラ)
当帰(トウキ)、桂皮(ケイヒ)、芍薬(シャクヤク)、木通(モクツウ)、細辛(サイシン)、甘草(カンゾウ)、大棗(タイソウ)、呉茱萸(ゴシュユ)、生姜(ショウキョウ)
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】の効能効果(ツムラ)
しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):足腰の冷えに
- 桂枝茯苓丸㉕(けいしぶくりょうがん):足が冷えてのぼせる人に
- 大建中湯(だいけんちゅうとう):お腹の冷えに
- 五積散(ごしゃくさん):クーラー病にも効果あり!
- 真武湯(しんぶとう):新陳代謝が低下した虚弱体質の人の冷えに
- 苓姜朮甘湯(りょうきょうじゅつかんとう):腰まわりが冷えて痛みがある人に
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】の特徴・説明
- 『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』は体質的に手足が冷えやすい方で、冷えると症状が悪化するような場合に使用されます。
冬場であれば、「しもやけ」などに、夏場であれば、「クーラーでの冷え」などに使用されます。
血行をよくして冷えた体を温め、冷えによる痛みをとります。

クーラーの設定温度が低すぎるのもつらいよね⤵
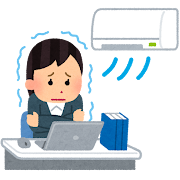
- 『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』は末梢血流を改善することで体を温め、鎮痛・鎮痙・健胃などの作用を示します。
- ”四逆” の「四」とは四肢、「逆」とは逆冷のことを指していて、体の末端から冷えが上がっていくことを意味します。
- 『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』の味は表現法が難しいですが、わずかに甘くて辛いです。
ストレス性冷え性のサイン「手足が冷える」を見逃すな!
寒い季節だけでなく、年中手足が冷えることに悩んでいる方は少なくありません。
その原因の一つとして挙げられるのが、ストレスによる冷え性です。
ストレスが引き金となり、自律神経のバランスが乱れることで、血流が悪化し、特に手足の冷えを感じることが多くなります。
これを放置すると、体調全般にも悪影響を及ぼす可能性があります。
ストレス性冷え性のサインである「手足が冷える」を見逃さないために、その原因と対策を理解し、早めに適切な対応をすることが重要です。
本記事では、ストレスが原因の冷え性のメカニズムと効果的な対策法について詳しく解説します。
ストレス性冷え性のメカニズムと対策

ストレスが引き起こす様々な健康被害はよく知られていますが、実は「冷え」もその一つです。
ストレスが原因で手足が冷えるという経験をしたことがある方も多いでしょう。
そのメカニズムを理解することで、適切な対策を講じることができます。
ストレスがかかると、人間の自律神経のうち、交感神経が高まります。
交感神経が活発になると、心拍数の増加、血管収縮、瞳孔散大、汗の分泌増加など、身体活動が活発になります。
これにより血管が収縮し、血流が悪化することで手足が冷えるのです。
さらに、体の仕組みは巧妙で、交感神経に対抗する副交感神経も存在します。
急に交感神経が刺激されると、その反動で腸の運動が活性化し、腹痛や下痢が起こります。
自律神経の乱れは、腸の調子を乱し、便秘や下痢を引き起こすことも多いです。
過敏性腸症候群のような症状がある場合、自律神経のバランスを整えることが根本的な解決策となります。
ストレスで交感神経が高まり、血管が収縮すると血流が悪くなり、手足の末端まで血液が巡らず、手足が冷える状態が続きます。
これがストレス性冷え性の原因です。慢性的なストレスによる冷え性を改善するためには、ストレス管理とともに、適度な運動やリラクゼーション、バランスの取れた食事などが重要です。
ストレス性冷え性のサインである「手足が冷える」を見逃さず、早めに対策を講じることで、健康を維持しましょう。
体温の乱れを感じたら要注意!ストレスが原因かも?
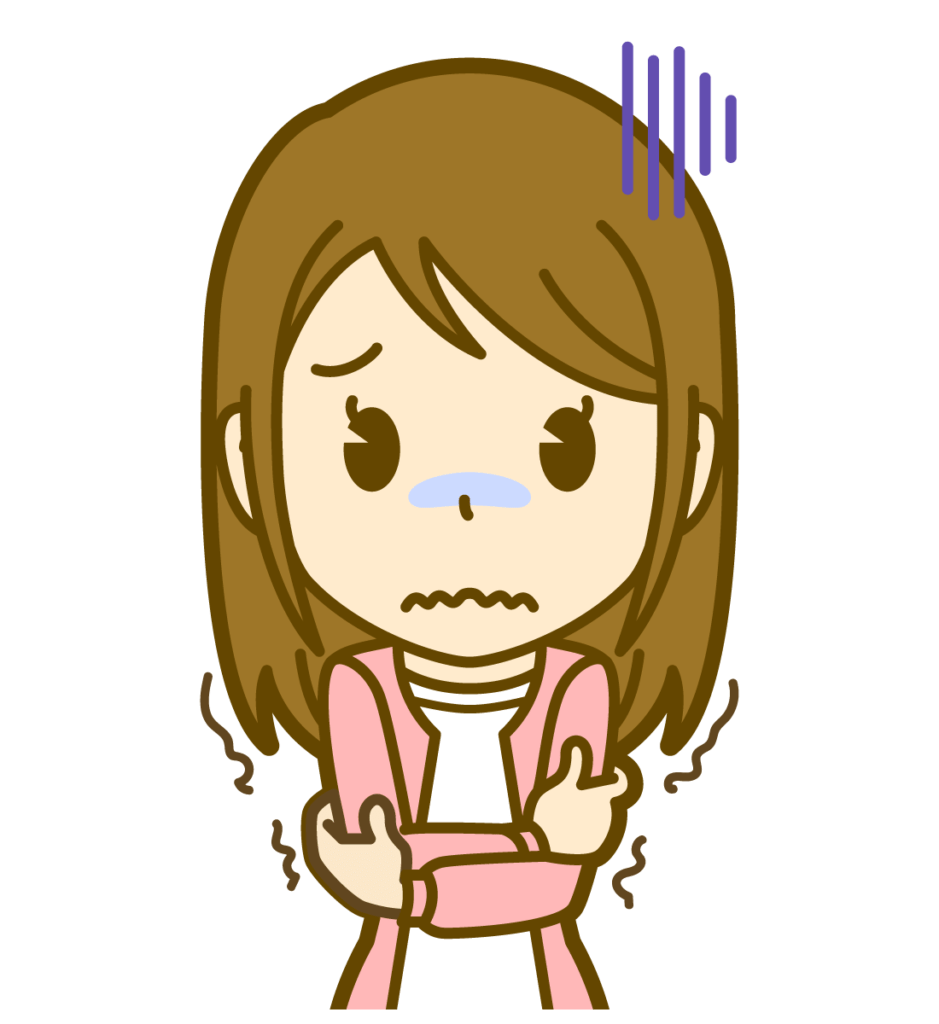
職種によっては、不規則なシフト制や夜勤がある方も多く、特に看護師さんに多いのがストレスによる低体温です。
ストレスと一言で言っても、精神的なストレスだけでなく、肉体的なストレスも含まれます。
不規則なシフト制や夜勤は、肉体的に相当なストレスを引き起こし、特に女性の場合は基礎体温にその影響が顕著に現れます。
ストレスがかかっている方の基礎体温表は、見事にガタガタ・ギザギザになります。
こんな時には、ストレスに対応する『加味逍遥散(かみしょうようさん)』などの漢方薬が有効です。
飲み始めて数日から1週間ほどで体温が上がったと感じる方も少なくありません。
基礎体温が乱れている場合、低体温が気になるよりも「無月経」や「生理不順」などの症状が現れることが多いです。
病院で検査を受けると「多嚢胞性卵巣症候群」や「高プロラクチン血症」と診断されることもあります。
これまで「生理不順」や「高プロラクチン血症」と診断された方から、「実は低体温だったけど、漢方薬を飲んで体温が上がった」という報告が多く寄せられています。
ストレスによる体温の乱れに悩んでいる方は、漢方薬を試してみると良いかもしれません。
怒りで全身が冷えるのは漢方の理論では「肝」の反応です

怒りの感情で全身が冷えた感じがするというのは、漢方の理論では納得の反応です。
東洋医学には「五情(心)」という考えがあり、それぞれに該当する「五臓(体)」があります。
- 怒=肝
- 喜=心
- 思=脾
- 悲=肺
- 驚=腎
漢方では「肝・心・脾・肺・腎」の五臓に体の機能を分類して考えます。
これはあらゆる全てのものを「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類して考える「五行説(ごぎょうせつ)」を人の体に応用したもので、非常に理にかなった部分があります。
このうち、「肝」は肝臓はもちろん、自律神経やホルモンバランスに関係します。
5つの感情のうち、怒りすぎると肝を損なうとされます。
怒りすぎると「肝」が乱れ、自律神経の乱れにより血管が異常に収縮し、全身に血流が巡らず冷えを生じる状態になるのです。
漢方的にはとても納得のいく体の反応です。
このような場合には「肝」の高ぶりを抑える『抑肝散』、『抑肝散加陳皮半夏』という漢方薬が有効です。
これらの漢方薬を服用することで、怒りによる全身の冷えが改善されることが期待できます。
冷え性の原因がストレス?漢方薬で対策しよう

ストレスによる冷え性の場合、滞った「気」を通すことが大切です。
そんな時は、『四逆散(しぎゃくさん)』という漢方薬を使います。
四逆散には、「柴胡(さいこ)、芍薬(しゃくやく)、枳実(きじつ)、甘草(かんぞう)」の4つの生薬が配合されており、即効性があります。
漢方薬は構成生薬数が少ない方が即効性が期待できます。
手足がキンキンに冷える、ヒステリー、胃腹痛、頭痛などの時に頓服で飲むこともあります。
しかし、慢性的なストレスによる冷えが続くと、手足の末端だけでなく肘や膝あたりまで冷えてくることがあります。
こうした場合には、『当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)』という漢方薬が有効です。
この処方は、四逆散よりも直接的に温める生薬が含まれており、より効果的に体を温めてくれます。
冷え性に悩む方は、これらの漢方薬を試してみてください。
ストレスによる冷え性を改善し、日常生活を快適に過ごせるようになります。
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】のクリニカルパールを紹介!
クリニカルパール(Clinical pearl)とは、経験豊富な臨床医から得られる格言のようなものです。
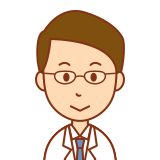
老人の内鼠径ヘルニアの人に筋肉の緊張を調整する作用を期待して『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』を使用することがあります。
(引用:漢方.jp)
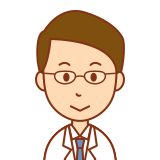
性交痛に『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』が効いたことあります。
(引用:漢方.jp)
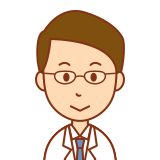
冷え性であり、月経困難症があるような女性の頭痛に『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』が良く効くことがあります。
また、なかなか治らない遷延した腰痛で足の冷えが強い場合には『当帰四逆加呉茱萸生姜湯』が良い場合があります。
(引用:漢方.jp)
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】の注意点
むくみ・体重増加・血圧上昇などが現れた場合は医師・薬剤師に相談するようにしてください。
【当帰四逆加呉茱萸生姜湯】の入手方法
- 病院で処方してもらう
- ドラッグストアや楽天・Amazonなどのインターネットで購入できます。
手足の末梢の冷えを根本的に改善するには「体の内外からのアプローチ」がポイント!

冷え性が酷い場合は、手足が冷えているからといってそこだけを温めても根本的な解消にはつながりにくいのです。
大切なのは ”全身から冷えを改善すること” が手足の冷えも含めたつらい冷え性を根本的に改善する近道となります。

体の内外からの根本的な対応が、冷え性改善の第一歩なんだね!
冷え性は体の内外から温めることが大切!冷え性改善におすすめの生活習慣TOP3!


体を温める生活習慣は、効果が出るまで気長にコツコツと続けていくことが大切です!
大きな関節を動かし冷え性改善!大きな筋肉を使えば手足の先までもポカポカに!

肩や股関節といった体の中でも大きな関節には大きな筋肉がついているので、少し動かすだけでも冷え性に対して大きな効果が得られます。
大きな筋肉には血管もたくさん張り巡らされているため、こまめに動かすことで効率よく血流が促されるのです。

2021年「東京ノービスボディビル選手権大会」にて見事に優勝したお笑いタレントの「なかやまきんに君」がYouTubeチャンネル【ザ・きんにくTV /The Muscle TV】にて「世界で一番温まる簡単ウォーミングアップ」というタイトルで紹介してくれていたよ!
冷え対策には「首」「肩甲骨まわり」「太もも」を中心に温めるのがポイント!

スカーフやマフラー・ネックウォーマなどで首を温めると、体の熱が逃げるのを防ぐことが出来て自律神経を整えるのに効果的です。
また、大きな筋肉のある肩甲骨まわりや太ももは血流が盛んな場所なので、ここを温めることで効率よく冷えの改善につながります。
特に太ももは、スパッツやレギンスなどのインナーウエアの上からカイロを貼るようにすると、冷え対策に効果的です。
冷え対策には ”体を温める食材” を取り入れることが大切!

人参やゴボウ、山芋などの根野菜やカボチャなど体を温める食材を意識して摂ることで、体の内側から温めることが出来ます。
発酵食品も体の代謝を良くしてくれるため、体を温めてくれます。発酵食品として代表的なものは、味噌や納豆です。

逆に、夏野菜の代表格でもあるトマト、きゅうりは体を冷やす食材と言われています。


またまた、「なかやまきんに君」がYouTubeチャンネル【ザ・きんにくTV /The Muscle TV】にて「寒い季節を乗り越える最強の筋肉食が完成です。
神セブンの〇〇で冷え性、便秘、風邪、減量などなどを乗り越え、体も心も温まります」というタイトルでおすすめの「筋肉スープ」を紹介してくれています!


「宮崎県川南町」に位置する「ほどよい堂」において、「薬剤師×中医薬膳師×ペットフーディスト」として、健康相談を行っています。
代表の河邊甲介は、漢方医学、薬膳、そして腸活を組み合わせた独自のアプローチで、個々の健康に寄り添います。
漢方相談や薬膳に関するオンライン相談も提供し、遠方の方々も利用できます。
また、わんこの健康も見逃しません。
わんこ腸活に関するアドバイスも行っています。
「ほどよい堂」で、健康に関する様々な疑問や悩みを解決しませんか?
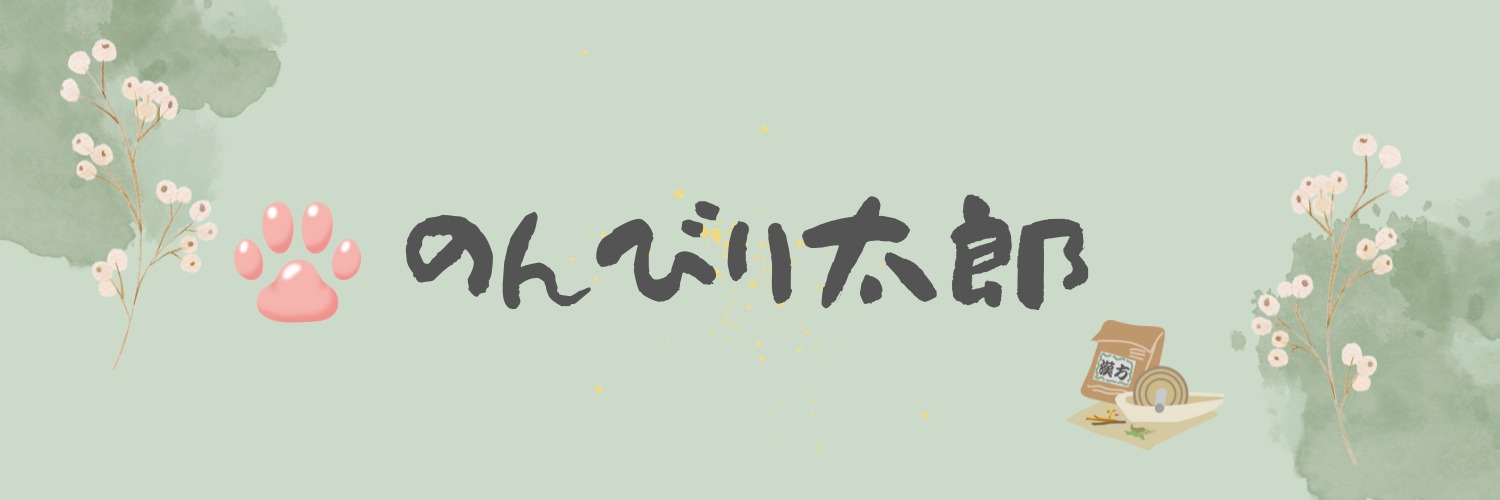






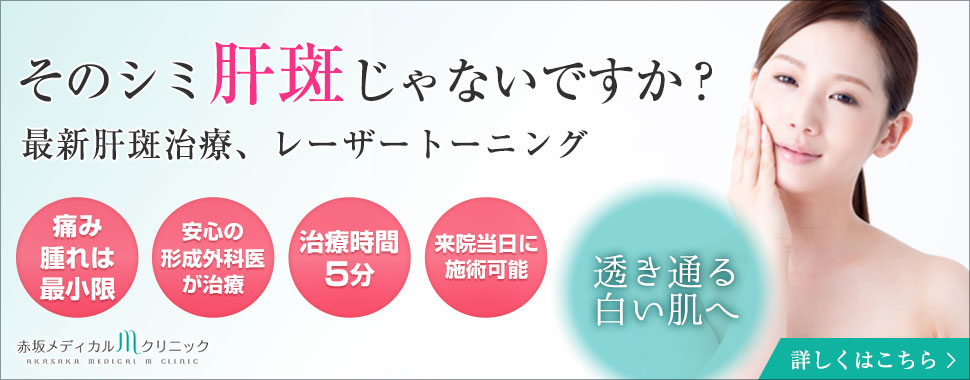

コメント