動物との触れ合いは、私たちの心に安らぎ・癒しを与えてくれます。
この動物が持つ癒しの力を借りて、心身を健康に導くのが「アニマルセラピー」です。
アニマルセラピーとは、動物を介して心身の健康を促進する治療法のことです。
犬や猫、馬などの動物が利用され、ペットとしての効果だけでなく、訓練された動物が患者とのふれあいを通じて治療効果をもたらします。
アニマルセラピーは、古代ローマ時代から馬を用いて負傷した兵士のリハビリが行われていた歴史があり、現在では人にとって身近な動物である犬を用いたセラピードッグの訪問が、高齢者施設や病院などで行われています。
日本では、セラピーと言うと単なる癒しと思われ勝ちですが、実は本来は「治療・療法」と言う意味なのです。
アニマルセラピーとは、本来「動物が医師を通して患者の機能向上の手助けをする」事が目的です。
日本アニマルセラピー協会では、既に国立病院の緩和ケア病棟を訪問し、患者さんのリハビリのお手伝いや痛みの軽減などに、実績を挙げています。
アニマルセラピーの中でも、医療現場で医療従事者の主導のもとに動物を用いる治療を「動物介在療法」と言います。
(引用:NPO法人日本アニマルセラピー協会)

動物を単純に見ているだけでも、癒されたり・元気が出たりするよね!

アニマルセラピーは、近年注目を集めている新しい治療法の一つです。
動物とのふれあいや交流が、人々の心身の健康に驚くべき効果をもたらすことが知られています。
本記事では、アニマルセラピーの癒しの力について、驚くべき効果とそのメカニズムについて解説します。
- ストレス軽減:動物との触れ合いがストレスホルモンの分泌を抑制し、リラックス効果をもたらします。
- 心理的安定:動物とのふれあいが心の安定をもたらし、抑うつや不安症状の緩和に役立ちます。
- 社会性向上:動物とのコミュニケーションが社交性やコミュニケーション能力の向上につながります。
- モチベーション向上:動物との関わりが楽しく、治療やリハビリのモチベーション向上に貢献します。
- 愛情と信頼:動物との触れ合いが愛情や信頼関係の構築を促し、心の安定をもたらします。
- ペットとしての効果:飼い主との絆や責任感が、心身の健康にプラスの影響を与えます。
- 生物学的影響:動物とのふれあいが体内のオキシトシンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促し、ストレスや不安の軽減につながります。
認知症に対する「アニマルセラピー」の効果

動物とのふれあいが人にもたらす効果については、「身体的効果」と「精神的効果」が過去に報告されています。
具体的には、社会性の改善効果として動物による話題提供、会話の促進をする「社会的潤滑油効果」があります。
例として、「高齢者が犬を連れて散歩していると、連れていないときより会話が増える」「他者との交流の機会のない長期療養患者や施設入所者が、動物の訪問をきっかけに会話や交流ができる」などがあげられます。
また、精神的作用として動物は人々に対して自尊心、責任感、必要とされている気持ち、自立心や安堵感、笑いや楽しみをもたらし、ストレスや孤独感を癒すというストレスの緩衝作用があることから、認知症の方や高齢者の社会性を高め、介護者の負担を軽減する可能性が期待されています。
(引用:循環器心身症の心身医学的アプローチ法 飯田俊穂Jpn J Psychosom Med60:417-424, 2020)
ホースセラピー(乗馬療法):馬の力で心と身体を癒す
アニマルセラピーの一種であるホースセラピーは、近年注目を集めています。
馬を使ったこのセラピーは、ストレス解消や心の癒しに加えて、子供の学校への不登校や引きこもりなどにも効果があります。
実際に、「子供が自信を持てるようになった!」、「不登校だった子供が学校に行けるようになった!」といった声が多く聞かれます。
さらに、身体に障害を持つ方にも馬に乗ることで身体の状態が改善される効果が認められており、障害者乗馬としても注目されています。
【ホースセラピーの効果】
ホースセラピーの主な効果は次のとおりです。
- ストレス解消:馬とのふれあいや乗馬がリラックスをもたらし、ストレスを軽減します。
- 自信の向上:馬との関わりや乗馬が自信を養い、心の強さを育みます。
- 不登校や引きこもりの解消:乗馬療法によって、学校への不安や抵抗が減り、子供たちが学校に通えるようになることがあります。
- 身体機能の改善:馬の動きや乗馬が筋力やバランス感覚を養い、身体機能の向上に寄与します。
【ホースセラピーの仕組み】
ホースセラピーの効果の背後には、馬の特性が関与しています。
- 馬の温もりと包容力:馬は温もりや安心感を与え、人々の心を癒します。
- 運動効果:馬の動きが人の体に良い刺激を与え、筋力やバランスを改善します。
- コミュニケーションと信頼関係:馬とのコミュニケーションが信頼関係を築き、心のつながりを深めます。
ホースセラピーは、馬とのふれあいや乗馬を通じて、心と身体を癒す素晴らしい治療法です。
心の癒しや自己成長を求める方々にとって、一つの有益な選択肢となることでしょう。
ペットの「チカラ」には無限の可能性が!

家庭でペットを飼う事も、アニマルセラピーの一種です。
事実、ペットを飼っている人は飼っていない人より、年間20%前後病院に行く回数が減ったと言うデータがあります。
ドイツでは7500億円、オーストラリアでは3000億円もの医療費が、ペットの影響によって削減されています。
生理的・身体機能的作用として人が動物に対しての働きかけをしようとする意欲から、日常の運動や動作が多くなり、動物に対する話しかけにより発語が増え、「飼い犬との時間は高齢者の血圧を低下させる」「ペットを飼っている人のほうが飼っていない人より収縮期血圧および血中コレステロール値が低い」という報告もあります。
アメリカ心臓病学会の 2013 年の報告でもペットを飼うこと、特に犬と暮らすことは、心血管病リスクの低下においてリーズナブルであるとのエビデンスを出しています。
循環器心身症に限らず循環器疾患全般においても動物とのふれあいの効果は、予防、長期予後の観点からも期待できる可能性が期待されています。
(引用:循環器心身症の心身医学的アプローチ法 飯田俊穂Jpn J Psychosom Med60:417-424, 2020)
セラピー犬とは

アニマルセラピストと共に、高齢者施設、障がい者施設、学校、病院、養護施設、刑務所などを訪問し、人々の心を癒すお仕事をする犬のことをいいます。
基本的なしつけがされており、人が大好きな犬たちです。

アニマルセラピーの活動の一部を紹介するね!アニマルセラピーについてもっと知りたいときは『日本アニマルセラピー協会NPO法人』のホームページを見てみるといいよ!

難病の子を支えるワンコ。東京の病院で初めて導入されたファシリティ・ドッグの1年間のダイジェストです。
セラピー犬の地位向上がこれからの課題!

欧米ではすでに多くの医療現場において、セラピー犬は治療・リハやビリ等で大活躍しており、その効果は目を見張るものがあります。
セラピー犬による医療費の大幅削減の報告もされています。
一方、日本ではセラピー犬の地位がまだ確立されておらず、セラピー犬の認知度が低いのが現状です。
セラピー犬の医療犬としての活躍の場を広げ、また、セラピー犬を公共施設等に同伴できるようにするため、セラピー犬について多くの方にご理解いただけるようセラピー犬の地位向上が期待されています。
(引用:NPO法人日本アニマルセラピー協会)
人々を癒やしてくれるセラピー犬ですが、犬にはストレスにならないの?


人には癒しを与えてくれるセラピー犬だけど、ワンちゃんはどう感じているのかな?

小児がん病棟のセラピー犬を科学的に調査、最大規模の研究結果が次のように発表されました!
結論から話すと、セラピー犬は「仕事」でストレスを受けておらず、むしろ楽しんでいる場合が多いみたいです。
研究結果の詳細は、次の通りです。
学術誌「Applied Animal Behaviour Science」に掲載された研究によると、小児がん病棟のセラピー犬は100人以上の患者を訪問し、26匹のセラピー犬が参加しています。
研究チームが測定したのが、イヌの唾液に含まれるコルチゾールの値です。
このホルモンは、ストレスに反応すると値が上昇する傾向があります。
その結果、病院にいるときと自宅にいるときで、研究に参加したセラピー犬のコルチゾール値に変化は見られず、セラピー犬が特にストレスを受けているわけではないことが明らかになっています。

ただ、セラピー犬に向いた性格の犬と向いていない犬がいることも事実であって、向いていない犬にはセラピー犬としての仕事はストレスにもなり得るということだったよ。
アニマルセラピーの向き不向き:受ける側と提供する側の観点から

アニマルセラピーは、人にとって効果的な治療法である一方で、受ける側や提供する側によっては向かない場合もあります。
そのため、以下のポイントを考慮することが重要です。
【受ける側の観点】
- アニマルセラピーに向かない人:
動物に危害を加えたり、暴力を振るってしまう人、アレルギー体質や感染症リスクが高い人、精神面で悪化を招く恐れのある人はアニマルセラピーに向かない場合があります。 - 個々のニーズを考慮する:
受ける側の個々の状況やニーズを考慮し、アニマルセラピーが適切かどうかを判断します。必要に応じて、医師や専門家との相談を行いましょう。
【提供する側の観点】
- アニマルセラピストの適性:
アニマルセラピストには、動物とのコミュニケーション能力や安全管理能力が求められます。高齢者や病気を抱えた人々との接触に慣れ、適切なケアを提供できる能力も重要です。 - 個々のニーズに対応する:
提供する側は、受ける側のニーズや制約を理解し、適切なサポートを提供することが求められます。状況に応じてセラピーの内容や方法を調整し、安全かつ効果的なセッションを提供します。
アニマルセラピーの効果は大きいですが、受ける側と提供する側の向き不向きを考慮することが重要です。
適切な判断と配慮を行い、安全かつ効果的なアニマルセラピーを提供しましょう。
アニマルセラピー 受けたい時はどうすればいいの?

アニマルセラピーを受けたいと思った時、以下の手順に従って行動することがおすすめです。
- インターネットで検索する:
アニマルセラピーを提供している施設や団体を探すために、インターネットで検索を行います。キーワードに「アニマルセラピー」や「動物介在療法」を入力し、近くの施設や提供者を探します。 - レビューや口コミを確認する:
施設や提供者の信頼性やサービスの評判を知るために、レビューや口コミを確認します。他の人々の体験談や感想を参考にすることで、安心して受けられるかどうかを判断します。 - 施設や提供者に問い合わせる:
興味を持った施設や提供者に直接問い合わせを行います。サービス内容や料金、予約方法などについて詳しく問い合わせることで、自分に合ったアニマルセラピーを受ける準備を進めます。 - 予約をする:
施設や提供者とのやり取りを経て、希望する日時にアニマルセラピーを受けるための予約を行います。人気のある施設では、予約が埋まってしまうこともあるため、早めに予約をすることが大切です。 - セッションを楽しむ:
予約した日に施設や提供者を訪れ、アニマルセラピーのセッションを楽しみます。動物と触れ合いながらリラックスした時間を過ごし、心身の健康をサポートします。
以上の手順に従うことで、自分に合ったアニマルセラピーを受ける準備を整えることができます。
自分のニーズや希望に合った施設や提供者を選び、心身の健康を癒すための素晴らしい体験を楽しんでください。
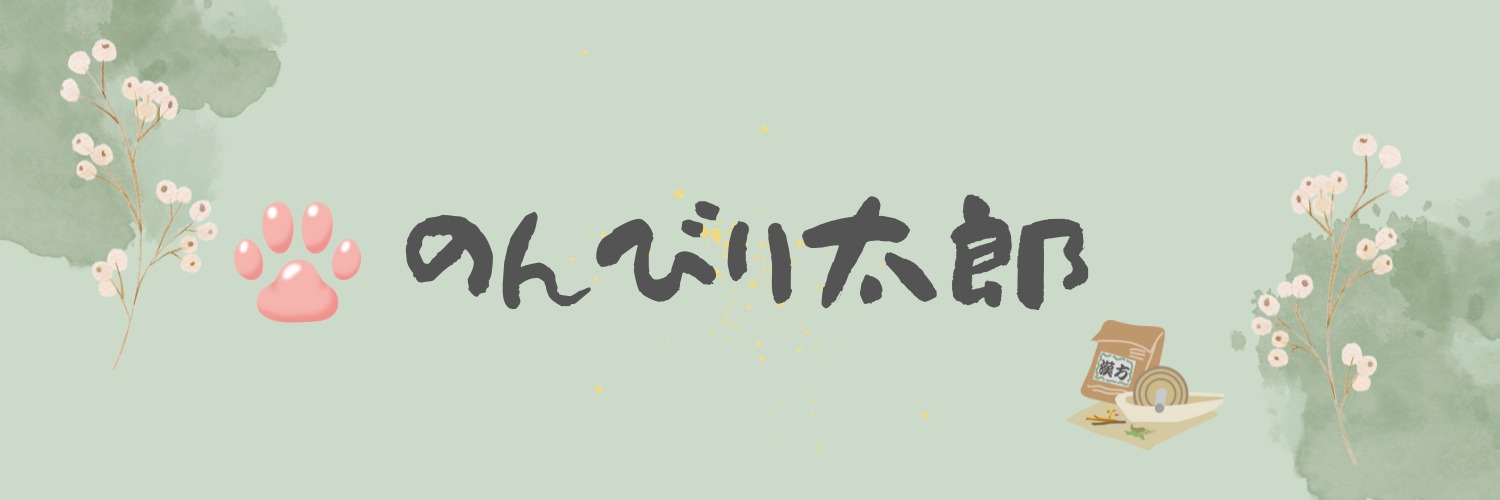



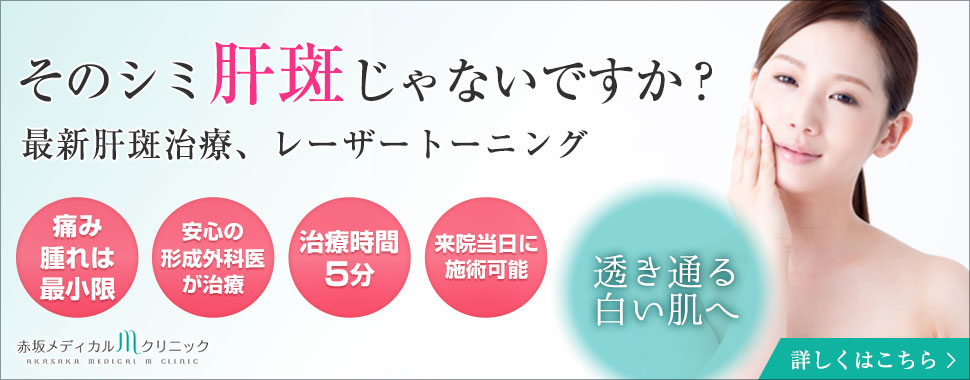

コメント