薬剤師にとって、「漢方薬」は切っても切れないものですよね!
ただ、医師もそうですが薬剤師も漢方薬に対しては、好き嫌いが激しい感じの印象があります。
そんな自分は、新人薬剤師の頃は漢方薬があまり好きになれず、勉強もほとんどしてきませんでした。
というのも、それは漢方薬の性格にありました。
なんと読むのか分からないような「生薬」や「気・血・水」だの「陰陽」だの、西洋医学では正確に説明できないような概念があってなんか胡散臭い!
かの有名な『葛根湯』を例に挙げると、効能効果は「感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患(結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎)、肩こり、上半身の神経痛、じんましん」です。

「いったいどんな成分が、どう作用したらこんなにも様々な効果がでるのだろう…?」って感じがしませんか?
やっぱりなんだか胡散臭い…。
そんな漢方嫌いの薬剤師であった自分が、漢方薬に興味を持ち始めたきっかけが自分自身の体調不良でした。
長らく心身ともに体調不良が続いていました。
病院で検査してもこれといって体調不良の原因が見つからない…。
しかし体調不良も一向に改善の兆しがない…。
そんな八方ふさがりの状態になったときに、以前は毛嫌いしていた ”あの漢方薬の性格” が逆に頼もしく感じました。
漢方治療は兎にも角にも、まずはなんとか今のつらい症状を解放していこうとするアプローチ方法なのです。
原因が分かっていても分からなくても関係なし!
漢方治療は原因が分からなければ治療が出来ない西洋医学とは全く異なる治療なのです。

漢方薬は原因も分からず、なかなか体調が良くならないで悩んでいるあなたには、まさに『希望の光』になると思います!


今回はそんな自分が、漢方薬を独学するにあたって役立ったおすすめの「漢方薬に関する書籍」を紹介してみようと思います。
漢方学舎白熱教室 入門編(源草社)【大野修嗣(著)】
『漢方学舎白熱教室 入門編』は写真やイラスト満載で、漢方薬の体系的なイメージをつかむにはおすすめの一冊だと思います。
漢方を学ぶ入門書としてぜひ購読して欲しい著書の一つです!
『漢方学舎白熱教室 入門編』を一通り目を通していると、漢方薬がどのような患者さんに使用され、どのような感じで効果を感じられるのかが理解できてくると思います。

『漢方学舎白熱教室 入門編(源草社)』は漢方薬を勉強しようと思ったときに最初に手にしたい一冊ですね!

「漢方学舎白熱教室 入門編 」の目次
- 西洋医学と漢方医学
- 漢方の基礎理論
- 六経理論
- 気血水
- 漢方実践応用
『漢方学舎白熱教室 入門編』の著者である大野修嗣先生の紹介
- 日本における臨床漢方医の第一人者としての全国での講演及び出版、インターネット等を通して漢方医学の普及に尽力。
- 国際東洋医学会理事(2021年現在)
- 大野クリニック院長
- 「e-漢方塾」と冠したネットでの症例カンファレンス形式の漢方議論を立ち上げる。
大野修嗣先生の主な著書を紹介!
- 『狭心症・心筋梗塞の中医学的治療』(朝日新聞出版サービス)
- 『膠原病・免疫疾患漢方治療マニュアル』(現代出版プランニング)
- 『漢方学舎入門編』(源草社)
- 『漢方学舎実践編1,2』(源草社)
※「e-漢方塾」での症例カンファレンス形式の漢方議論を著書に書き下ろしてあり、多くの漢方医が処方選択するまでの意図や経緯がわかり、実践に役立ちます。
3秒でわかる漢方ルール(新興医学出版社)【新見正則(著)】
『3秒でわかる漢方ルール』は ”生薬から漢方の世界を推論する” という著書の趣旨をもとに、著者である新見正則先生が、経験則によって導かれる「漢方ルール」を書き下ろされています。
生薬の足し算である漢方薬は、生薬レベルからの法則を会得すれば、短時間で漢方薬の性質が理解できるという内容になっています。
「漢方15分類チャート」などを筆頭に「虚実のルール」「寒熱のルール」「気血水のルール」など様々なルールが体系的にわかりやすく解説してあります。

「傷寒論」などのちょっと取りつきにくい書籍を読んで漢方が嫌になる前に、最初に漢方薬を勉強する際には『3秒でわかる漢方ルール』を購読してもらうといいと思います。
『3秒でわかる漢方ルール』の著者である新見正則先生の紹介
- 慶應義塾大学医学部卒業後、英国オックスフォード大学で移植免疫学を学ぶ。
- 専門は血管外科・消化器外科。
- セカンドオピニオンのパイオニア。
- 2013年、イグノーベル賞医学賞を受賞。
- 漢方の魅力を西洋医の立場からモダン・カンポウとして啓蒙。
- 漢方薬の魅力をYouTubeチャンネル「漢方.jp」にて配信されています。
※歯に着せぬ語り口で楽しいチャンネルですよ!
新見正則先生の主な著書(その他多数)を紹介!
- 『鉄則モダン・カンポウ』(新興医学出版社)
- 『3秒でわかる漢方ルール』(新興医学出版社)
- 『実践3秒ルール 128漢方処方分析』(新興医学出版社)
- 『フローチャート薬局漢方薬』(新興医学出版社)
- 『スターのプレゼン 極意を伝授! 』(新興医学出版社)※分担著書
- 『ボケずに元気に80歳!: 名医が明かすその秘訣 』(新潮文庫)
臨床医のための漢方薬概論(南山堂)【稲木一元(著)】
『臨床医のための漢方薬概論』は、漢方薬の伝統的な使い方から、近年の研究成果までが包括的に書き下ろされてあります。

稲木一元先生は、漢方薬とは ”知の地図を作り上げる作業の結果” と表現されていました。
『臨床医のための漢方薬概論』の著者である稲木一元先生の紹介
- 日本赤十字社医療センター内科(1987~83)、財団法人日本漢方医学研究所附属渋谷診療所副所長(1993~2002)、青山稲木クリニック院長(2002~17)を経て、東京女子医科大学東洋医学研究所講師(2005~17)を歴任。
- 2021年現在は新宿つるかめクリニックと日本赤十字社医療センターで漢方外来を担当。
『臨床医のための漢方薬概論』の集約内容紹介
- 現在の伝統的使用法
- 実際に用いた症例
- 鑑別処方
- 最新エビデンス
症候による漢方治療の実際(南山堂)【大塚敬節(著)】
『症候による漢方治療の実際』は、いわゆる ”漢方薬の辞書” 的な一冊です。
漢方薬について何かわからないことがあったら、まずは『症候による漢方治療の実際』で調べてみるというスタンスで自分は利用させてもらっています。

『症候による漢方治療の実際』は、「国語辞典」「英和辞典」のようなサイズ感とボリューム感です。

『症候による漢方治療の実際』の著者である大塚敬節先生の紹介
- 昭和期の漢方復権に尽力した代表的な日本の医師。
- 東洋医学の発展に貢献した業績により1978年に日本医師会より最高優功賞を日本で初めて受賞。
- 終戦当時、中国からの輸入が途絶えがちとなり生薬の入手が困難になったため、敬節はそれに代わるものを求めて民間薬、国産生薬・家伝薬に関する研究にも力を注ぎ、その成果が後に『民間薬療法と薬草の智識』(長塩容伸、大塚敬節、1957年)や『漢方と民間薬百科』(1966年)などの出版につながる。
漢方ポケット図鑑(源草社)【宮原桂(著)】
『漢方ポケット図鑑』には日本国内で非常によく使われる漢方49処方と、生薬全82種が収載されています。
漢方薬の構成生薬を、写真と美しい水彩イラストで紹介しているため、一目で分かります。
漢方薬の正体を、ビジュアルで解説した便利図鑑として手元に置いておきたい一冊です。
日本図書館協会選定図書にも選ばれています!
読書があなたの人生を変えるかもしれない⁉

無限の『インプット』・『アウトプット』を可能にするのが読書です!
今、あなたが手にしているその1冊があなたの人生の転機になるかもしれません!
読書をすることのメリットとして次のようなことが挙げられています。
読書によってストレスが軽減するという効果は、「ビブリオセラピー(読書療法)」として実用化されています。
ビブリオセラピーとは、牧師で人気エッセイストでもあったサミュエル・マッコード・クローザーズ氏が提唱した概念で、読書によって病気の治癒を図るという心理療法です。
今の自分の状態に適した本を読むことで、行動をよい方向に変えたり、苦痛を減らしたりするなどの効果が期待できることが科学的にも実証されています!
スキマ時間でもいいので読書を習慣化すると良さそうですね。
まとめ

今回は、漢方薬を勉強するにあたって自分が利用して役立ったおすすめの書籍を紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?
本はたくさんの知恵やヒントを与えてくれますので、スキマ時間などにちょっとでも本を読んでみると何か変化が起こるかもしれません。
今回紹介した書籍が少しでもあなたのお役にたてれば嬉しいです。
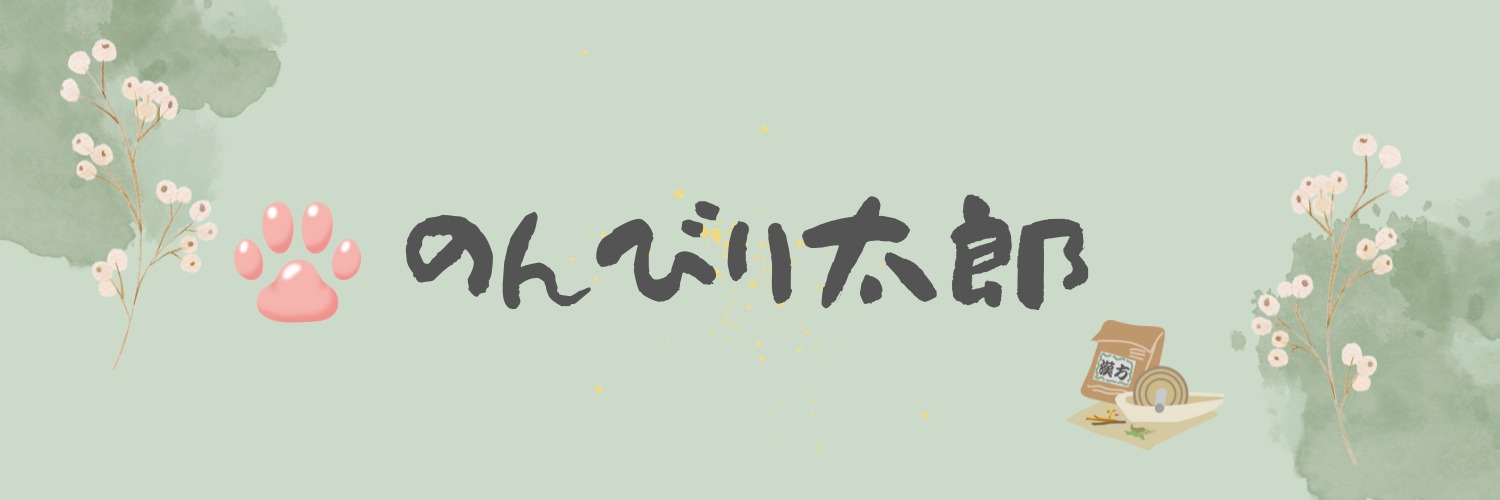
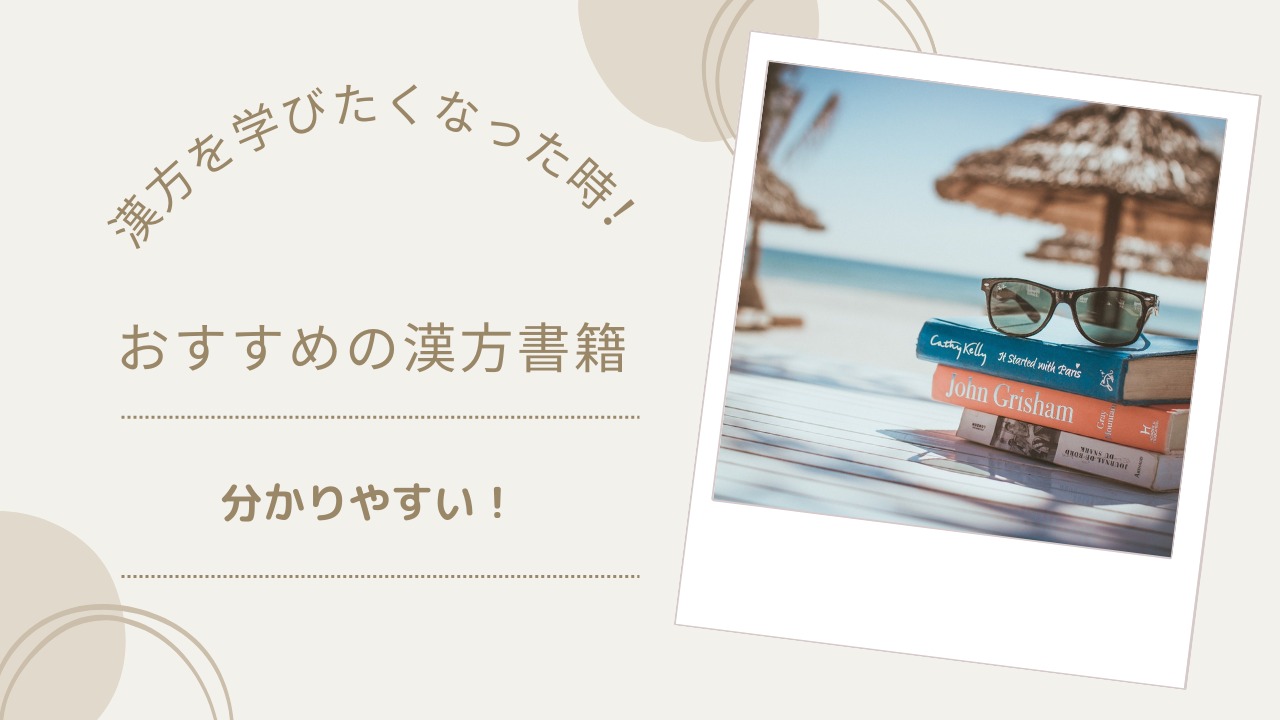
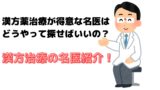


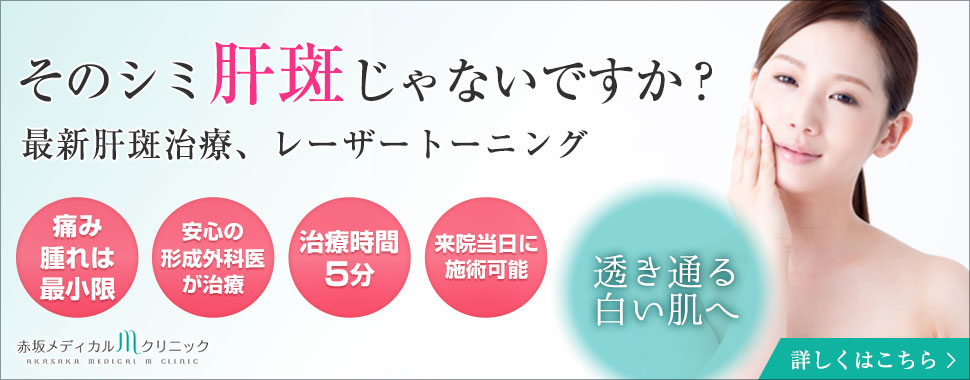

コメント