あれこれと思い悩む取り越し苦労が多く、不眠・驚きやすい・憂うつ・不安などの精神的症状のほか、胸やけ・食欲不振などの消化器症状があるひとにおすすめの漢方薬が『温胆湯 (うんたんとう)』です。
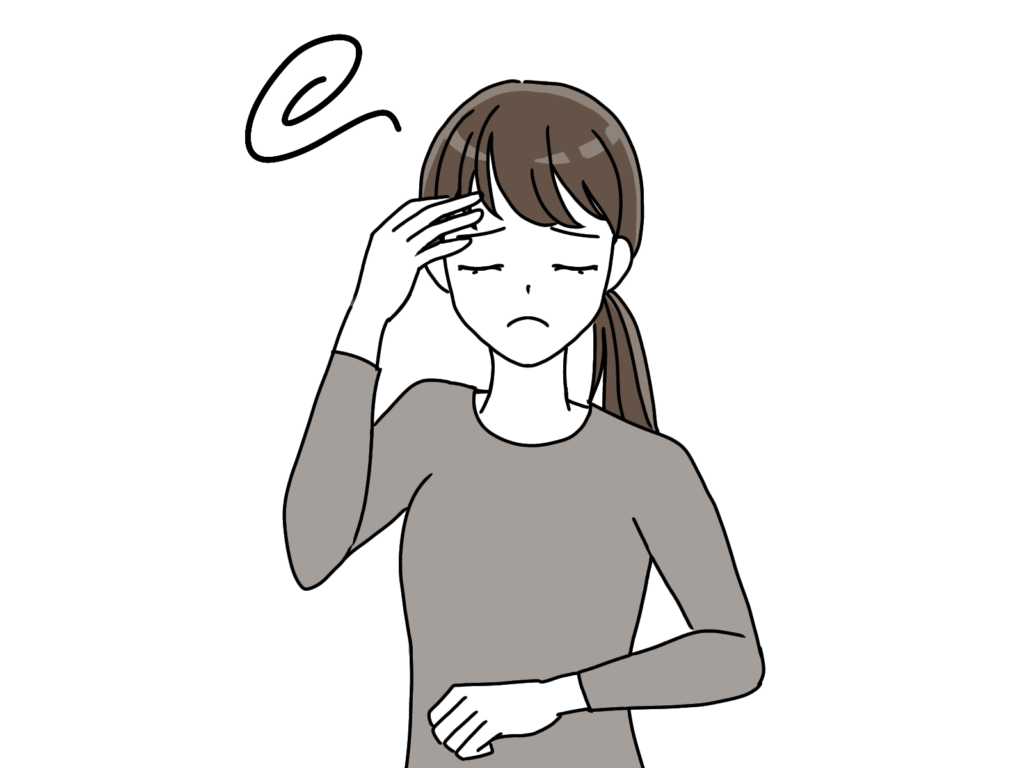
温胆湯 (うんたんとう)の生薬構成
生姜(ショウキョウ)、竹茹(チクジョ)、甘草(カンゾウ)、陳皮(チンピ)、枳実(キジツ)、半夏(ハンゲ)、茯苓(ブクリョウ)
温胆湯 (うんたんとう)の効能効果(イスクラ)
体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症:不眠症、神経症
温胆湯 (うんたんとう)の特徴・説明
- 燥湿化痰(ソウシツカタン:痰と余分な水分を除く)の『二陳湯』に清熱化痰(セイネツカタン:痰を除き熱を冷ます)の「竹茹(チクジョ)」と理気の枳実「(キジツ)」を配合したもの。
- 熱と結びついた痰熱は、体内の気血水の循環を滞らせて、不眠・頭痛・めまい・胸やけ・食欲不振を引き起こすと考えます。
- 『温胆湯』は痰熱を除き、痰熱が引き起こす精神症状や消化器症状を改善する作用が期待できます。
さらに、胆を強めて胆力(決断力)をつける作用も兼ねています。

のんびり太郎
「胆(キモ)が据わる」という言葉があるくらいで、胆は決断力を主る腑であると中医学的には考えられています。
胆の機能が虚すると物事にビクビクして、不安を感じるようになります。
胆が失調することは不眠につながると考えます。
温胆湯 (うんたんとう)の入手方法
ドラッグストアや楽天・Amazonなどのインターネットで購入できます。
リンク
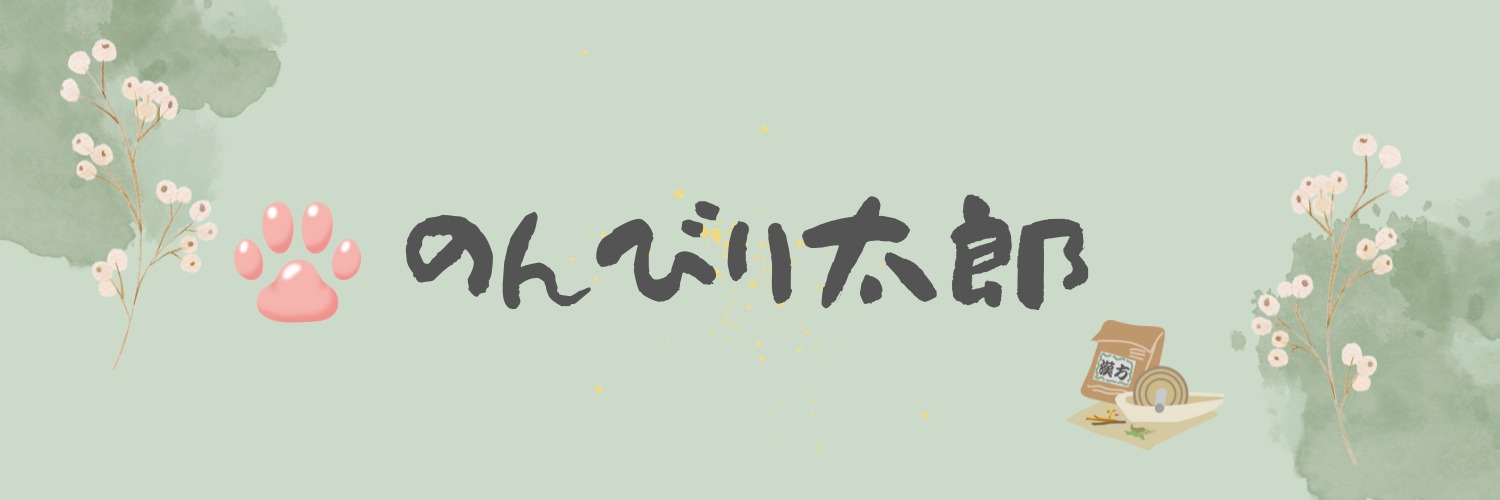

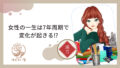

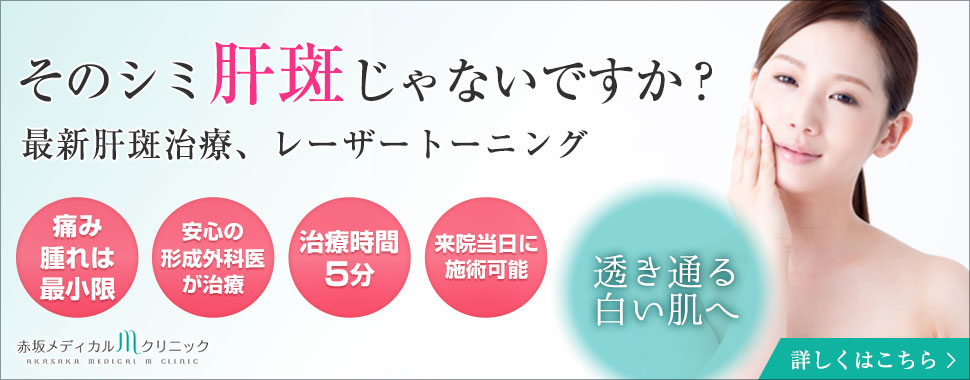

コメント