杏(あんず)は、バラ科サクラ属の落葉小高木で、アプリコットと英名で呼ばれることもあります。
β-カロテンが豊富に含まれており、体内ではビタミンAとして働くため目や皮膚の健康を保つ効果があります。
そのほか、消化器などの粘膜を丈夫にすることで、外部からの細菌類の侵入を防ぐ役割を持ちます。
また、ミネラル類やビタミン類、食物繊維も豊富に含まれているため、便秘解消や貧血予防にも効果的な薬膳素材です。

特にβカロテンはとても多く、多く含まれている代表的な果物「みかん」の約5倍ほどあります。

杏(あんず)の薬膳データ

- 体質:気虚・陰虚
- 五性:温(微温)
- 五味:甘・酸
- 帰経:肺・大腸・肝・腎
データの項目の見方

薬膳の観点からの区別とその食材に合う体質が分かります。
五味(ごみ)
薬膳における五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味(塩辛い味)の5つの味のことです。
五味はそれぞれに対応する臓腑があり、その臓器に吸収されやすいといわれています。
- 酸味 – 肝 – 胆
- 苦味 – 心 – 小腸
- 甘味 – 脾 – 胃
- 辛味 – 肺 – 大腸
- 鹹味 – 腎 – 膀胱
五性(ごせい)
薬膳における五性とは、食材や生薬がもつ体を温めたり冷やしたりする性質のことです。
寒 / 涼 / 平 / 温 / 熱 があり、寒・涼の食材は体を冷やし、温・熱は体を温めます。
平は体を温めたり冷やしたりする性質のどちらもありません。
帰経(きけい)
薬膳における帰経とは、食材や生薬がどの臓腑・経絡に入り効果的に働くかを示した道しるべです。
臓腑や経絡、精神に影響を与えるといわれています。
個々の体質に合う帰経の食材を取り入れることで、体を良い状態に近づけられると考えられています。
体質(体質)

体質は、気滞体質 / 気虚体質 / 瘀血(血瘀)体質 / 血虚体質 / 痰湿体質 / 陰虚体質 / 湿熱体質 / 陽虚体質の8つに分かれ、それぞれの体質によっておすすめの食材や養生法が異なってきます。
その時の体質に合った食材・生薬を摂ることで体を良い状態に近づけられると考えられています。
杏(あんず)の栄養成分

以下に、杏(あんず)の栄養成分とその健康効果を表にまとめます。
| 栄養成分 | 詳細 | 健康効果 |
|---|---|---|
| ビタミンA(ベータカロテン) | 豊富に含まれる | 視力の維持、免疫機能の向上、皮膚の健康 |
| ビタミンC | 抗酸化作用がある | 免疫機能を高める、皮膚の健康維持 |
| ビタミンE | 強力な抗酸化物質 | 細胞の老化防止 |
| カリウム | 血圧を調整 | 血圧の正常化、筋肉の機能サポート |
| 鉄 | 赤血球の生成に必要 | 貧血予防 |
| マグネシウム | 神経系と筋肉の機能を維持 | 神経系と筋肉の正常な機能維持 |
| カルシウム | 骨と歯の健康を維持 | 骨と歯の健康維持 |
| 食物繊維 | 豊富に含まれる | 消化を助ける、便秘予防、血糖値の調整、コレステロールの低下 |
| 抗酸化物質(フラボノイド、ポリフェノール) | フリーラジカルを中和 | 細胞損傷の防止、抗炎症作用、心血管系の健康サポート |
| 糖質 | 天然の糖分を含む | 即時エネルギー源 |
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 視力の改善 | ビタミンAとベータカロテンが夜盲症を防ぎ、視力を維持 |
| 心臓の健康 | カリウムと抗酸化物質が血圧を正常に保ち、動脈硬化を予防 |
| 免疫力の向上 | ビタミンCとビタミンAが免疫システムを強化し、感染症から守る |
| 消化の促進 | 食物繊維が腸内の健康を保ち、便秘を防ぐ |
| 皮膚の健康 | ビタミンA、C、Eが皮膚の健康を維持し、老化を遅らせる |
夜盲症の予防・改善効果
杏(あんず)にはβ-カロテンが豊富に含まれています。
β-カロテンは体内でビタミンAに変化するため、特に夜盲症の予防や視力低下の抑制などに効果的であることが知られています。
そのほか、抗酸化作用があり、紫外線や酸化ストレスから皮膚を保護し、老化を遅らせる役割があります。
また、炎症を抑制し、がんや慢性疾患のリスクを軽減する可能性があります。
貧血を予防する効果
杏(あんず)には鉄分が含まれ、貧血予防や血液の酸素供給向上に寄与します。
ヘモグロビンの構成成分である鉄は、酸素を体中に運び、健康な赤血球の生成に不可欠です。
食事に杏を取り入れることで、鉄の適切な摂取が促進され、エネルギー代謝や免疫機能の維持にも寄与します。
便秘を解消する効果
杏(あんず)に含まれる食物繊維は、腸内環境を整え、便通を促進します。
食物繊維は腸内で水分を吸収し、便を柔らかくし排便をスムーズにします。
また、血糖値の上昇を緩やかにし、コレステロールを低減する効果があり、糖尿病や心血管疾患の予防に寄与します。
さらに、食物繊維は満腹感を促進し、過食を防ぎ、体重管理にも役立ちます。
あんずを食べることで、健康的な腸内環境の維持や様々な代謝機能の向上に寄与することが期待されます。
摂取の注意点
- 乾燥杏の摂取: 糖分が濃縮されているため、糖尿病のリスクがある人やダイエット中の人は摂取量に注意が必要。
- アレルギー: 初めて食べる場合は少量から始めるのが良い。
杏(あんず)を使ったおすすめレシピ







おすすめレシピは ”COOKPAD(クックパッド)” から引用しています!
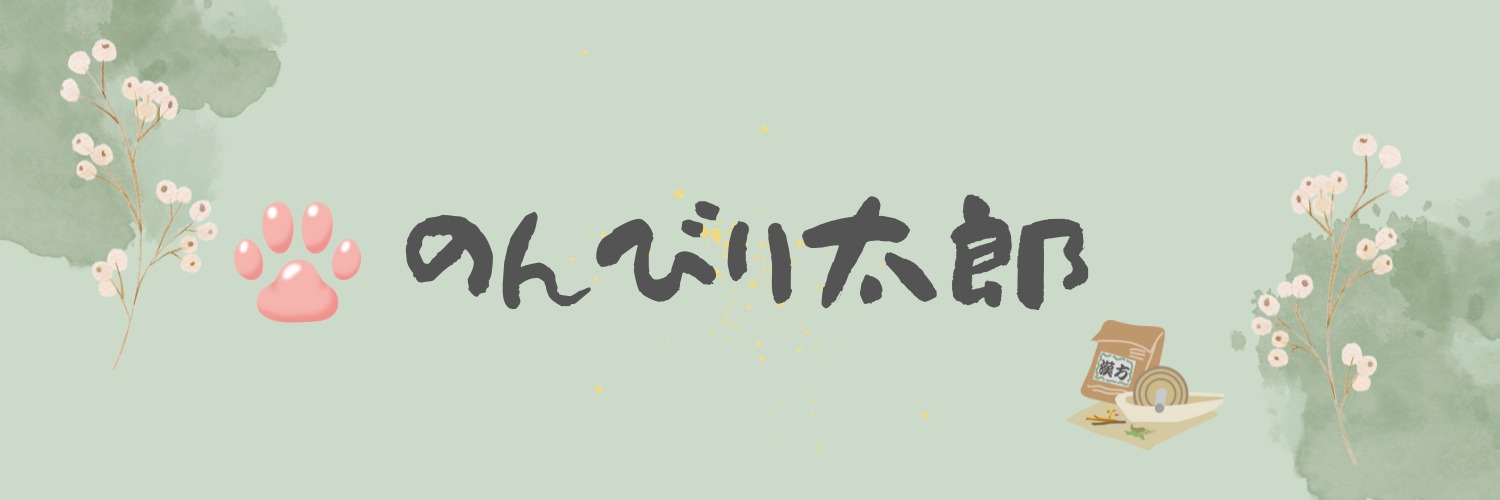








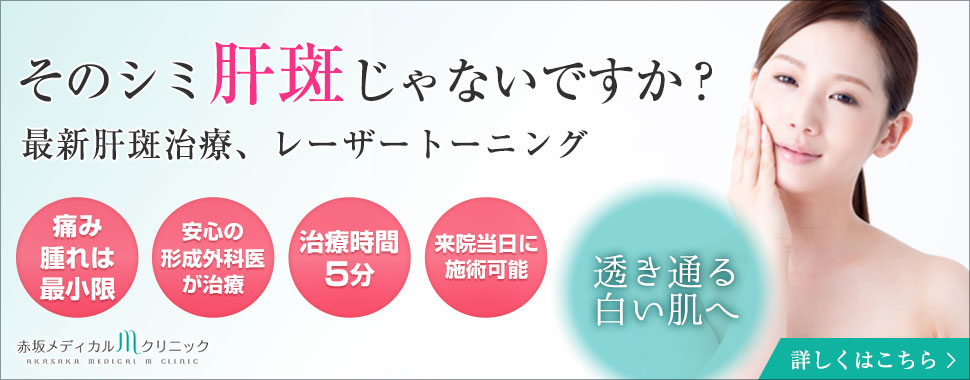

コメント